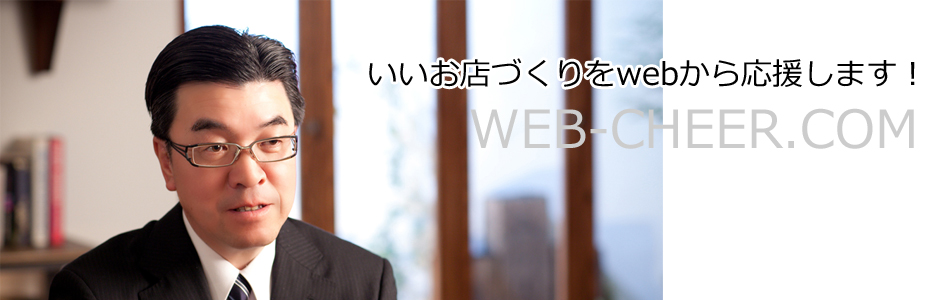ホームページ集客・SEO対策マスターの村岡です。
アニメーションを表示したり、特殊な機能を追加するなど、
様々な用途に使える機能にJavaScriptというものがあります。
多くのホームページがこの機能を利用しており、
ウェブの分野においては、欠かせないものにナッツています。
しかし、検索エンジンのほとんどは、
JavaScriptのデータを認識しないことから、
SEOの側面から見た利点は少ないのが実情です。
特にJavaScriptのデータを記入することで、
キーワードの密度が下がるのはデメリットと言えるでしょう。
しかし、実はこのリスクはJavaScriptのデータを、
外部ファイルにすることで解消できます。
JavaScriptも外部ファイルから参照する仕組みにできるのです。
これでHTMLからJavaScriptのデータを分離し、
キーワード密度を高めることができるので、
JavaScriptを使っているページではぜひ実行しましょう。
また、JavaScriptのデータを検索エンジンが認識しないということは、
言い換えれば、その内容がページの評価につながらないということです。
そこで活用したいのが、<noscript>タグです。
<noscript>タグは、JavaScriptに対応していない、
ブラウザでアクセスされたときのために、
代わりの情報を記述しておけるタグです。
JavaScript対応のブラウザでは機能しませんが、
対応していないブラウザでは記述しておいた情報を表示します。
つまり、JavaScriptが機能しない時にフォローできるのです。
もちろん、検索エンジンはページの情報として認識してくれるので、
<noscript>タグでJavaScriptと同じ情報を記述しておけば、
その内容を検索エンジンにも伝えることができます。
検索エンジンへの情報伝達と、JavaScriptに対応していない、
ブラウザへの対応を兼ねて、<noscript>タグの情報も記述しておきましょう。
以上参考にしてくださいね。
ホームページ集客
ウェブチアー 村岡栄紀
>>弊社ホームページはこちら
ホームページ集客・SEO対策に役立つ「ガイドブック」無料プレゼント!
御社のホームページを「無料診断・アドバイス」受付中!